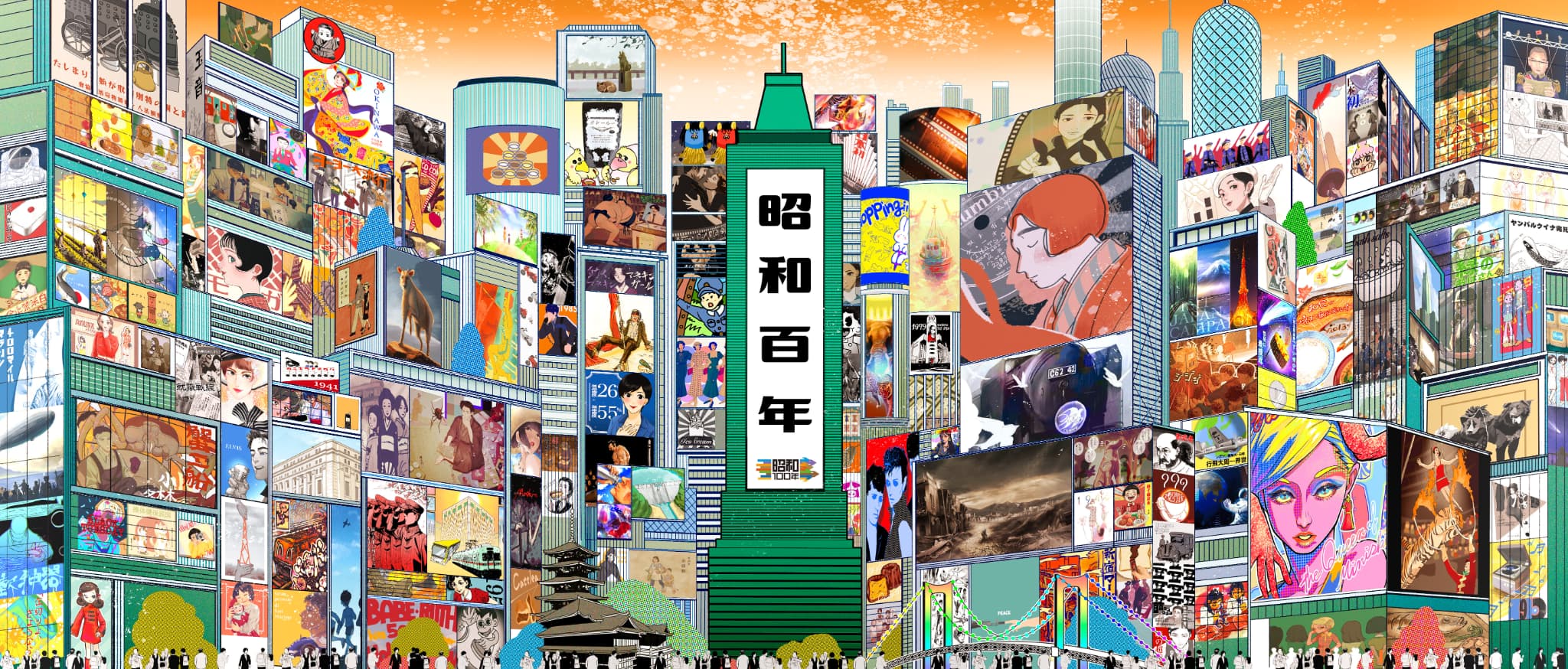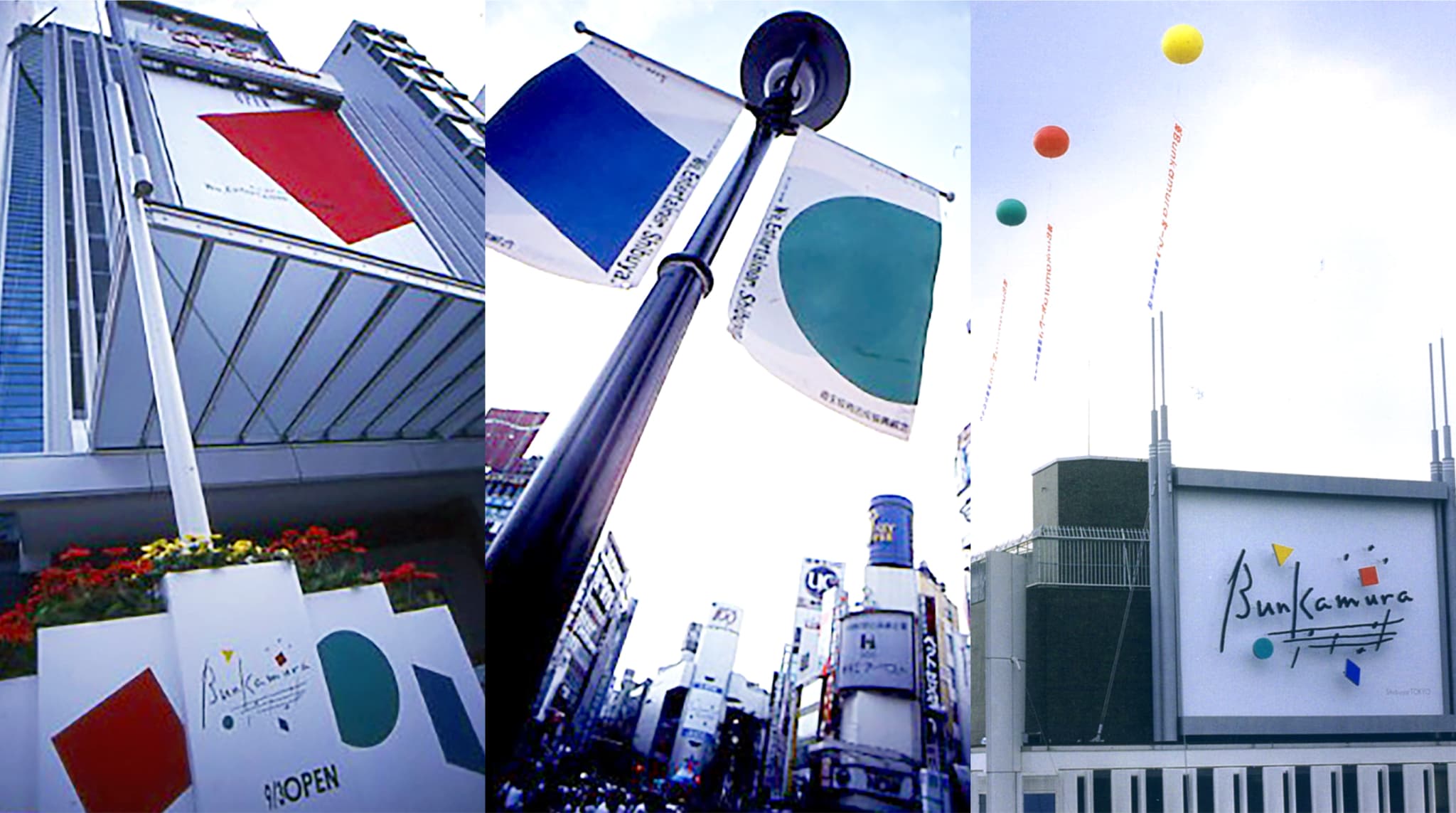ロカビリーブーム ――SNSがない時代の奇跡――

日本のロカビリーブームは誤解から始まった!山下敬二郎の『ダイアナ』が大ヒットし、「ロカビリー三人男」が熱狂を生んだ歴史を振り返る。
世紀の大ブームは勘違いから始まった
1950年代初頭。
アメリカ南部で産声を上げたロカビリーが日本中を席巻したのは、「もはや戦後ではない」に象徴される50年代後半のこと。ウエスタン歌手の山下敬二郎が、ポール・アンカの『ダイアナ』を革ジャン姿でカバーし、大ヒットしたのがきっかけでした。
ただし、この話にはオチがあります。実は『ダイアナ』はロカビリーではなく、アイドル・ポップスとされる曲だというのです。当時は情報が少なく、言葉の壁もあり、アメリカからくる音楽はすべてロカビリーだと誤解されていたのです。
そんな勘違いをものともせず、山下に平尾昌晃、ミッキー・カーチスを加えた「ロカビリー三人男」は大人気に。
出演した1958年(昭和33年)2月8日の音楽フェスティバル「日劇ウエスタンカーニバル」では、熱狂的なファンが大量の紙テープを投げ込み、興奮したファンが彼らを客席に引きずり込んでいる様子が、当時の映像に残っています。
そこから2月8日は「ロカビリーの日」とされ、今でもフェスやイベントが行われ、配信でも聴けるようになったことから、若いファンの姿も見られるようになりました。
刺激的なサウンドに加え、前髪を膨らませたポンパドールヘアや革ジャンなどのファッションは、当時世界中の若者たちを虜にしたように、現代の若者たちをも魅了しています。